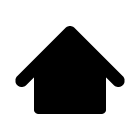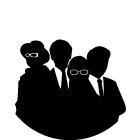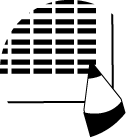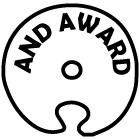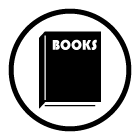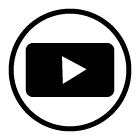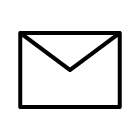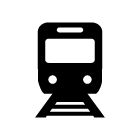空間 構造 デザイン研究会
直近の開催研究会

第56回AFフォーラム+KD研1-15
「建築と技術(構造)―ANDの来し方、行方」
日時:2025年04月12日(土)14:00~コーディネータ:斎藤公男
パネリスト:磯達雄(建築ジャーナリスト)、堀越英嗣(建築家)、宇野求(建築家)
お申込み(リンク先にて会場参加orZoom参加を選択してください。):https://ws.formzu.net/fgen/S72982294/
Youtube:https://youtu.be/2PPyAZ4HZh4
アーキニアリング・デザイン(Archi‐Neering Design:AND)なる言葉とその理念が日本建築学会(AIJ)から初めて発せられたのは2007年。「建築学とデザイン力の融合」から提起された“AND”とは、ArchitectureとEngineering Designとの融合・触発・統合の有り様(プロセス)とその成果を意味している。ここから企画された「AND展」(2008年~)は全国9支部と海外(台湾、中国)、計20回の巡回展を実施した。古今東西の名作・傑作・話題作を集めた建築・構造模型(パネル)は200点をこえており、市民のみならず建築界においても、あらためて「建築」のもつ魅力と役割を強く共感・共有せしめたとの声が寄せられた。さらにANDの流れはA-Forumにおけるさまざまな活動やAND賞の設立へとつながっている。
21世紀もすでに四分の一を過ぎようとしている今日、20世紀の建築に比べ、最も影響を与えているものの一つは言うまでもなくコンピューターの進化と発展であろう。もはや、情報化時代ではなく情報化社会であり、デジタル技術やアルゴリズムの浸透スピードと多様性はとどまる処を知らない感がある。一方、時には方向性を疑う事や、過剰なエネルギーの浪費を促す危惧もあろう。BIMやAIはあくまで人間の思考や技術的判断、効率化のための手段(ツール)の一つ。それ以上の存在ではない、といった声も聞こえてくる。ITの可能性と課題についての議論は様々な分野で広がっている。
アーキニアリング・デザインの基本的テーマは建築(芸術)と構造(技術)の融合という、相対的ベクトルの有様や成果である。その主役はながらく人間力―建築家とエンジニア(構造家)とされてきたが、そこにツールを超えたコンピューターのパワーが介入し、三つ巴の様相が展開されているのが今日の状況といえよう。見方を変えれば情報化社会がANDの新しい展開を促しているようにも感じられる。
日本建築学会における2025年度の特別研究委員会「アーキニアリング・デザイン研究会」を立ち上げた背景の概要は以上述べた通りである。研究テーマを「情報化社会におけるアーキニアリング・デザインのゆくえ」とした。
今回のフォーラムは「研究会」の第一回キックオフ・ミーティングと共催する形で下記のように企画をした。併せてKD研(空間構造デザイン研究会)Part I 第15回の活動とも連携したい。(斎藤公男)
プログラム
プレゼンテーション(各30分)
① 「60年代の建築再評価 ―ブルータリズムの未来とは(仮)」 磯達雄
② 「それからの山本学治 ―70年代からの論考をめぐって(仮)」堀越英嗣
③ 「それからの建築・構造デザイン ―建築文化・特集(1990、1992)をふり返りながら(仮)」宇野求
プレゼンテーションの後、Q&Aと意見交換を行う
一覧
キックオフ
2021/09/04 第38回AF-Forum+第0回 空間 構造 デザイン研究会「熱く闘いし、構造家たち」 動画「内田祥哉(1925/5/2 - 2021/5/3)」 松村秀一 (東京大学大学院工学系研究科建築学専攻)
「川口衞(1932/10/21 - 2019/5/29)」 松尾智恵 (明星大学准教授、たにおか設計社代表取締役)
「播繁(1938/2/22 - 2017/9/5)」 中田捷夫 (株式会社中田捷夫研究室 代表取締役)
「渡辺邦夫(1939/12/2 - 2021/4/9)」 萩生田秀之 (株式会社KAP)、金箱温春(金箱設計事務所)
「新谷眞人(1943/10/12 - 2020/8/23)」森部康司 (yAt構造設計事務所、昭和女子大学准教授)
Part I
2021/10/30 第1回「鉄のデザイン」 動画「Gallery U/a、Gallery U/a、Works with Takahashi Gogyo 」岡田哲史(岡田哲史建築設計事務所、千葉大学院准教授)
「空に漂う鋼構造デザイン:KAIT広場、Zoorasiaレストラン棟、Cloud Arch、Lattice3 = Lattice×Lattice×Lattice、Jasmine Dimple」佐藤淳(佐藤淳構造設計事務所、東京大学大学院准教授)
「高橋工業の歩みと技術」高橋和志(高橋工業 代表取締役)
2021/12/04 第2回「メンブレンの空間と構造」 動画
「Botswana Project」阿知波修二 ( 隈研吾建築都市設計事務所 )
「膜構造の夜明けから現代まで ーゼネコンの構造設計者の立場から」西谷隆之(清水建設)
「膜構造の可能性(past-present-future」野口明裕(太陽工業)
2022/02/16 第3回「高層木造の可能性」 動画
「三菱地所グループの木造木質化事業の取組」海老澤 渉(MEC Industry、三菱地所設計、三菱地所)
「高層純木造耐火建築『OY Project』」百野 泰樹(株式会社大林組)
「木造の最前線と今後の展望」安達 広幸(株式会社シェルター)
2022/04/23 第4回「歴史的建造物のリノベーション」 動画
「歴史的建造物の耐震改修実例-富岡倉庫ー」江尻憲泰(江尻建築構造設計事務所、日本女子大学)
「京都市京セラ美術館について」西澤徹夫(西澤徹夫建築事務所)
2022/06/25 第5回「軽い木の特徴を活かした“モクビルプロジェクト”」 動画
「都市型中高層木造の可能性」加藤詞史(加藤建築設計事務所)
「構造 PART STARTS×MENSHIN」中西力(スターツCAM)
「木質材料・プレカット・構造木工事について」小野塚真規(オノツカ)
2022/08/06 第6回「CLTを用いた構造デザイン」 動画
「CLTが導く構造デザインの形」桝田洋子(桃李舎)
「CLTを用いた構造デザイン」蒲池健(KMC)
2022/10/22 第7回「3Dプリンタによる建築空間の可能性」 動画
「3D PRINTED HOUSES」曽野正之(Clouds Architecture Office)
「コンクリート3Dプリント施工技術を用いた住宅の設計:フジツボモデル」益山詠夢( 慶応義塾大学 特任准教授)
「セメント系材料を用いた3Dプリンターの開発」坂上肇(大林組)
「3Dプリンター実証棟」鈴木貴博(大林組)
2022/12/24 第8回「さらば”東・海”1974—東京海上日動ビルディングの都市・建築・技術をめぐって」 動画
「・前川國男と「東海」・前川氏との思い出」橋本功(前川事務所)
「街づくり:景観の背景」岩井光男(元三菱地所設計)
「構造計画について」小西義昭(小西建築構造設計)
2023/07/22 第9回「どうする、テンション_。ケーブル構造の魅力と可能性をさぐる」 動画
「私にとってのテンション構造―期待と課題」鴛海昂
「ケーブルの新しい可能性を拓く」北茂紀(20分)
「設計・施工の現場から「広島スタジアムをめぐって」
▹計画(基本構想・デザイン):松村正人 ▹構造設計:島村高平 ▹施工:小山聖史
「ケーブル構造の現状と対応」田川英樹
2023/11 第10回「特別企画 No.2「東北の空間構造を訪ねて」
鉄鋼技術2023年11月号 紙面にて報告
2023/12/02 第11回 「若き構造家達はいま」 動画
安藤耕作(ANDOImagineeringGroup)
川田知典(川田知典構造設計)
高橋寛和(コウゾウケイカクロナンナン)
2024/03 第12回「特別企画 No.3「出雲+鳥取の空間構造を訪ねて」
鉄鋼技術2024年06月号 紙面にて報告
2024/6/15 第13回「感性と技術とAIと― 空間と構造の交差点をめぐって」 動画
「効果的加速主義と効果的利他主義を超えられるのか」加藤詞史(加藤建築設計事務所) 「現代建築が忘れていること―失われていく五感の感覚」堀越英嗣(芝浦工業大学名誉教授、東京藝術大学客員教授/建築家)
「ネオ・クリエイティビティ(+共創)の探求 Exploring Neo-Creativity」松永直美(レモン画翠) 2025/04/12 第15回「建築と技術(構造)―ANDの来し方、行方」
「60年代の建築再評価 ―ブルータリズムの未来とは(仮)」 磯達雄(建築ジャーナリスト) 「それからの山本学治 ―70年代からの論考をめぐって(仮)」堀越英嗣(建築家) 「それからの建築・構造デザイン ―建築文化・特集(1990、1992)をふり返りながら(仮)」宇野求(建築家)
2024/9/12 第14回(特別版)「「私にとっての構造デザイン」-「建築 × 構造のおもしろさを語る会」in沖縄」 動画
第一部 講演会 「構想から建設へ-空間と構造の交差点」斎藤公男
第二部 座談会 「構造デザインの諸相をめぐって」斎藤公男・多田脩二・与那嶺仁志
会場︓那覇文化芸術劇場「なはーと小劇場」
主催︓(一社)建築構造技術者協会(JSCA) 沖縄地区会
共催︓(株)国建
後援︓(公社)沖縄県建築士会、(公社)日本建築家協会 沖縄支部、( 一社)沖縄県建築士事務所協会
Part II
2021/09/18 第1回「プロローグ ―空間構造への誘い」 動画2021/10/02 第2回「1960年頃―構造デザインの曙」 動画
2021/11/20 第3回「B.フラーとスペースフレームの世界」動画
2021/12/25 第4回「B.フラーとスペースフレームの世界 その2」 動画
立体トラス構造を拓いた人々
2022/03/19 第5回「奇跡のプロジェクト ー“代々木”と“シドニー”をめぐって」 動画
国立代々木競技場『代々木』(1964)、シドニー・オペラハウス『シドニー』(1973)、ミュンヘン・オリンピック競技場『ミュンヘン』(1972)、モントリオール・オリンピック競技場『モントリオール』(1976)、北京・オリンピック競技場『鳥の巣』(2008)、Z.Hの新国立競技場(案)『Z.H』(2012)
2022/05/21 第6回「IT時代のデザインをめぐる構造評論」 動画
・内藤廣「構造デザイン講義」をめぐって
・Z.H.の「新国立」を再考するー・プロセスと基本構想・多様な言説とAND展
・「代々木」からのメッセージとは
2022/07/23 第7回「手さぐりの空間構造(その1)―かたちとちから(A)」 動画
山形アーチのデザイン
下関市体育館 (1963)、秋田県立体育館(1968)、茨城県立武道館(1983)
2022/09/17 第8回「手さぐりの空間構造(その2)―かたちとちから(B)」 動画
・キールアーチとケーブルネット・岩手県営体育館をめぐって
2022/11/19 第9回「手さぐりの空間構造(その3)―ITへの取り組み」 動画
千葉商科大学体育館(1970)、笠松運動公園体育館(1974)
ゲスト:池田一郎(1965日大卒、 元S.H.C.R)、広瀬正行(1968日大院卒、元構造計画)、松林隆道(1969日大院卒、元フジタ)
2023/01/28 第10回「手さぐりの空間構造(その4) ―設計・製作・施工の相関」 動画
・スペースフレーム 「ポートピア’81 国際広場」・サスペンション膜「つくば万博’85 駅前シェルター」
ゲスト:岡田章、中島肇、真柄栄毅、工藤恭一、奥原剛彦、郷田哲雄
2023/03/18 第11回「ポストモダンからの脱出 ―張弦梁はどこから生まれたか」 動画
2つの張弦梁構造(BSS)
ファラデーホール(1978)、理工スポーツホール(1985)
2023/06/03 第12回「ポストモダンからの飛翔 ―サラブレッドからハイブリッドへ」 動画
IASS’86、グリーンドーム前橋‘90
ゲスト:宮田勝利、幕田圭一、小野里匡章
2023/09/09 第13回「テンセグリティを超えて」 動画
つくば万博’85/2つのプロジェクト ・富士通館と燦鳥館
2023/12/23 第14回「発想から建設まで(その1)」 動画
「天城ドーム」をめぐって ―フラーから有明へ
特別企画
2021/09/08 「船の体育館」(旧香川県立体育館)のいままでとこれから―再現計画から再生計画― 動画「経緯と方向性」名和研二(なわけんジム)
「保存運動に向けての状況」河西範幸(一般社団法人 船の体育館 再生の会)
「構造計算書から読み解く」田中正史(武蔵野大学)
発足にあたって
皆様ご存知のように、2013年12月に設立されたA-Forumは早くも今年末で8年目を迎えます。これまで運営・コアメンバーによりさまざまな企画が行われてきましたが、多くの方々の協力と支援のお陰で大きな成果をあげることができました。「AF-フォーラム」や「研究会」もそのひとつですが、昨今のコロナ禍の広がりの中で、通常の開催はなかなか難しく、運用の工夫が求められています。
此度、A-Forumの中心的理念である『建築(家)と技術(者)の融合』をテーマにした新しい研究会を、今回の第38回AF-フォーラム「熱く闘いし、構造家たち」(2021年9月4日(土)14:00~)をキックオフ・イベントとして立ち上げることにしました。 近年あるいは今年になって他界された身近な方々―内田祥哉先生、川口衞先生、播繁氏、渡辺邦夫氏、新谷眞人氏らはいずれも「松井源吾賞」あるいは「日本構造デザイン賞」を受賞された著名な建築家・構造家です。その業績が高く評価されることは言うまでもありませんが、それと共に真摯な人柄と熱き情熱、建築や構造デザインへの愛着といった志を次の世代へのメッセージとして伝えたい。そうした思いがこの研究会の設立をした原点です。
アーキニアリング・デザイン(AND)とは建築と技術を結ぶ二つのベクトル―融合・触発・統合の有様や成果を見つめようとする言葉ですが、「空間構造デザイン研究会(KD研)」にもその評価軸は通底しています。ここでは2つのテーマ、すなわち「空間と構造のデザイン」および「空間構造のデザイン」からヒントを得て、次のような2つのPartを設定してみました。
Part I :「空間と構造の交差点」…話題のプロジェクトやテクノロジーをめぐって
Part II :「“空間構造”の軌跡」…実践的挑戦と世界の潮流
まずPart Iでは、建築家とエンジニアの協同や技術的開発・挑戦から実現された様々な成果やそのデザイン・施工プロセスについて数名のパネリストからレポートして頂き、オンライン方式での質疑・意見交換を行う。
つぎにPart IIでは、1959年に設立されたIASS(国際シェル・空間構造学会)の主要なテーマとして今日に続いている“空間構造”(Spatial Structure)に焦点を当て、長年にわたるわが国の活動を解剖しつつ世界の動向を俯瞰すると共に、若い世代を含めたフリートークを楽しみたい。皆様のご参加をお待ちしています。