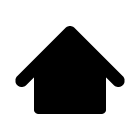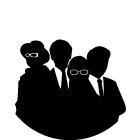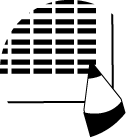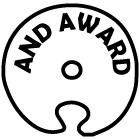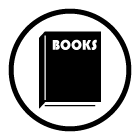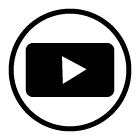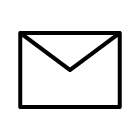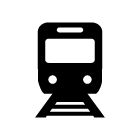第57回AFフォーラム「振動計測と耐震性」
日時:2025年06月17日(火)18:00~コーディネータ:神田順
パネリスト:
濱本卓司(東京都市大学名誉教授):内藤多仲はこう考える
楠 浩一(東京大学教授):建築物の構造ヘルスモニタリング
五十嵐俊一(構造品質保証研究所):常時微動と耐震計算・耐震補強
お申込み(リンク先にて会場参加orZoom参加を選択してください。):https://ws.formzu.net/fgen/S72982294/
Youtube:https://youtu.be/CSlkiBiBYzc
既存構造物を長く活用するためには、その耐震性の評価が重要である。耐震診断手法については、すでに一般化している一方で、地盤の評価の課題、中小地震による被害発生、超高層建築の耐震性評価など、まだまだ課題は少なくない。いろいろな立場から、過去にAFフォーラムにおいても議論して来ている。
動的な性能評価を明らかにしようとすれば、常時微動が便利であり、もちろん、中小地震時の地震応答計測もより有効な情報を提供してくれる。どの程度まで使用性が確保されるか、どの限界を超えると人命に影響がでるかなどは、それらの計測結果からは、直接には判断できないものの、単に設計時の計算結果の情報ではわからない現実の情報が多く含まれておる。先人の知見は、今日の設計法、耐震性評価法に大きく取り込まれている。 濱本氏は、内藤多仲が中心となって建物の振動計測を行った膨大なデータを、内藤の記述とともに改めて取りまとめ「内藤多仲の構造診断書を読む」(早稲田大学出版部)として刊行した。
楠氏は、RC構造物を中心に、ヘルスモニタリングについての研究を進めており、広く成果を発表している。
五十嵐氏は、従来行われている地震動に対する時刻歴応答解析に基本的な問題点を指摘し、一方振動計測から耐震性を評価し、SRF工法を開発し、すでに実績として多くの耐震補強を実践している。
理論と現実、動的特性と耐震性、設計と診断、などそれぞれの切り口で議論を整理しておくことは、大きな意義があると考え、本フォーラムを企画する