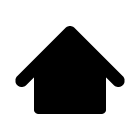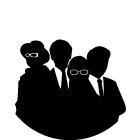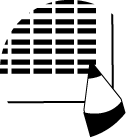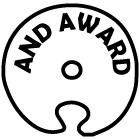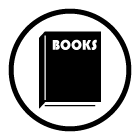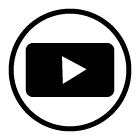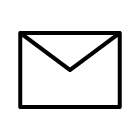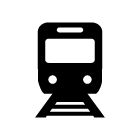第5回 アーキニアリング・デザイン・アワード 2024
選考委員
福島加津也(委員長)(東京都市大学教授/建築家)、陶器浩一(滋賀県立大学教授/構造家)、磯 達雄(建築ジャーナリスト)、堀越英嗣(芝浦工業大学名誉教授/建築家)選考評(総評) 選考評(個別) 冊子PDF
選考評(個別)
最優秀賞
十津川村災害対策本部拠点施設
応募代表者:藤村 龍至(RFA)共同応募者:金箱 温春(金箱構造設計事務所)

【応募理由】2011年の紀伊半島大水害で大きな被害を受けた奈良県十津川村の庁舎に隣接する、災害対策本部拠点施設である。私たちは十津川の民家に学びつつ、村内で伐採される材木の寸法から構造材の寸法を決め、非JAS材の全数検査を実施するなど十津川産材を用いるための具体的な提案を行った。AND賞ではデジタルファブリケーションや新素材など新たな技術的挑戦が評価されることも多いが、小さな自治体が公共事業でつくる比較的小さな建築における、地域の生産能力に応じた、優しい技術を用いた新たな社会的挑戦もまた、AND賞のもう一つのあり方としてふさわしいと考え、応募させて頂いた。丁寧にご選考頂きどうもありがとうございました。(藤村龍至+金箱温春)
【講評】建設地は2011年の台風12号による大きな被害を経て復興した山間の村である。林業が盛んであることから、地元で採れる木を使用した木造建築とすることが選ばれた。調達が可能な材は断面径や長さに制約がある。その条件下で村産材を最大限に活かせる構造システムとして導き出されたのが、村の村章でもある「菱十字」の形に柱と斜材を組み合わせる方法だった。斜材は垂木に連なって天井を形成する。さらに斜材は外側に延びて、深い軒やバルコニーを支え、災害対策本部に有益な、広い半屋外空間を建物周りに実現した。「菱十字」の構造は、内外に現れて、空間を規定する。また屋根勾配は周囲に見られる民家の外観とも呼応し、村の風景に建物を溶け込ませている。なお村産材はJAS材ではないため強度にもばらつきがあるが、個別に強度や含水率を確認し、構造計算に反映させたという。地域性が、材料、構造、意匠と、何層ものレベルで絡まった作品である。そして、木造建築の新たな提案を、屋根の架構だけでなく、建物全体のデザインとしてまとめ上げた点も高く評価したい。地域における中大規模木造のあり方を指し示したAND建築だ。(磯)
優秀賞
人工林の課題からつくられた小径間伐材の建築
応募代表者:吉田 敦(竹中工務店)共同応募者:田中 匠、金子 侑樹(竹中工務店)

【応募理由】本プロジェクトがアーキニアリングデザインという言葉にとても親和性を感じたことからの応募であった。昨今、建築領域における木造木質化の勢力は大きくなっている一方、脱炭素社会に資するという観点では本当にそうなのか?と疑問になる利活用事例も多いと感じることがある。森林側の生産体制に対しての妥当性、流通材にすらならない森林資源の課題など日本全国にひろがる人工林に対し無視されがちな課題を拾って生まれた計画の可能性を世の中に広げたい想いから応募した。デザインの観点だけでなくエンジニアリング色の入った賞であり、これまで得られなかった多くの発見もあった。改めて関係者みなさまに感謝申し上げたい。(吉田・金子)
【講評】現地に残る里山を中心とする希少な自然環境をフィールドとした環境学習のための施設。敷地内林の環境整備のために必要な人工林の間伐に伴う材を用いることを前提とし、材を無駄なく使い切ることを考えて設計が行われている。また、半径60km県内で製材を完結させた材を余すことなく用いることを目指している。集成材などを用いず小径材を組み合わせて大空間が設計されており、特に、75mm角材を用いた屋根架構が印象的である。単独では成立しない不完全なトラス架構をずらしながら交互に並べ、直交方向にはしご状の梁を挿入することにより、それらが一体となって大空間架構を成立させ、複雑な接合部をつくることなく軽快で特徴的な空間をうみだしている。木造トラス構造では接合部が複雑な金物で構成するようになりがちであるが、斜材同士は敢えて繋がず、直交材を挿入することで架構として成立させるアイデアが面白い。(陶器)
VOXEL APARTMENT
応募代表者:藤村 龍至(RFA)共同応募者:藤田 慎之輔(DN-Archi)

【応募理由】広島のまちなかに建つ集合住宅である。周囲には高層の集合住宅が立ち並ぶなか、容積率を消化することをせず、小さくてもまちのなかで存在感を放ち、共感を呼ぶようなあり方を考えた。スタディと解析を進めるうちキューブの集合による凹凸のある形態が生まれたが、その構造は階高を活かした「壁式フィーレンデールトラス」として解釈することになった。屋上スラブにCLTパネルを用いたが、そのディテールは木造住宅における基礎と大引きの関係にも似て、広島の施工者にも負担のない提案とした。そのような試行錯誤を選考のなかで「建築と社会の対話を感じた」と言っていただき、とても嬉しく思いました。ありがとうございました。(藤村龍至+藤田慎之輔)
【講評】都市の集合住宅は最大限の容積と有効率が求められることが多いため、周辺環境に対して矩形や箱型のボリュームで圧迫感を生み出しやすい形態となる性質を持っているが、この計画では集まって住むことで自然にコミュニケーションが生まれる場所を、建築内にとどまらす、敷地を超えた周辺環境との空間ボリュームを生み出す意図からスタートしている。それは設計者が述べている「まちを感じる家」としてのあり方を、建築の立体的ボリュームが作り出す 3D IN-BETWEEN スペースの追求で実現している。 この「間」の空間は階高のスケールの立方体格子の構造的フレームのリズムによって人々の日常が自然に顕れる開口部、テラス、バルコニー、回遊する外部階段、路地空間を生み出している。5,5mのキャンティレバーや柱のない3次元的な立体空間を成り立たせているのが、階高を利用したフィーレンデール立体トラスであり、複雑な立体的形態であることを敢えて活かした、部分が支え合う離散的構造体である。この土木的スケールの構造によりグランドレベルの空間領域がパブリックな領域として立体的に掘り込まれた稀有な都市の集合住宅の外部空間を生み出していることは特筆すべき提案である。(堀越)
YAP Constructo 07 -ノマディック ドーム
応募代表者:原田 雄次(ephemeral research)共同応募者:Claudio Torres、Clarita Reutter、Emile Straub(ephemeral research)、佐藤 淳、古市 渉平 (佐藤淳構造設計事務所)

【応募理由】このノマディックドームをチリで2017年に作った後、働いていたチリの建築設計事務所を辞めて日本に帰国しました。その時に一番はじめに声をかけていただいたのが斎藤公男先生方のA-forumでした。それから7年の月日を経て日本での移築を実現し、そのご報告とお披露目も兼ねて今回応募させていただきました。
審査会では審査員の先生方に組み立て方の問題点や課題を指摘していただき大変勉強になりました。同時に「美しい」という評価をいただき、とても嬉しく感じております。テンセグリティのみならず、エフェメラルな(儚い)ストラクチャの持つ魅力をこれからも探求していこうと思います。(原田)
【講評】この作品は、2017年にチリのサンチアゴで建てられたパビリオンである。テンセグリティ構造を応用した約300㎡の無柱空間が、3週間のワークショップでつくられた。学生たちによるセルフビルドのため、アルミパイプとスチールケーブルとの接合部に、寸法調整のためのターンバックルを設けて、組立だけでなく解体も容易にするための工夫がなされている。機能的な要請への実直な対応が、緊張感のある力の釣り合いを生み出し、アルミパイプが宙に浮いているような空間になっている。建築のつくりかたの工学的な検討の積み重ねが、美学的なデザインにたどり着いていることがすばらしい。2024年には、日本の山中湖に恒久的な施設として再建設されている。主要な部材をスーツケースに入れて、飛行機の手荷物でチリから日本に持ち込むという、まさに旅する建築だ。チリでのパビリオン的な機能に加えて、長期的な使用に対応する建築空間として、その使われ方はさらに拡がっていくだろう。いつかぜひ、私もこの透き通るような浮遊する空間を体験してみたい。(福島)
富士ソフト汐留ビル~現代化された組積造による都市型オフィス~
応募代表者:三橋 幸作(竹中工務店)共同応募者:田井 暢、柳澤 慎太郎、平尾 雅之(竹中工務店)

【応募理由】昨今のLCCO2削減、建築仕様・性能の高度化、レジリエンス向上等、複雑に絡まった建築的課題を解決するには、建築家のアイディアと各領域のエンジニアリングを統合しつつ最適化できる新しいシステムが必要だと感じ、私達は、ドミノ・システムが乗り越えた組積造建築に可能性を見出しました。富士ソフト汐留ビルは、「現代化された組積造」をデザインコンセプトとして新規開発された「千鳥積層型外殻PC架構」を軸とし建築と構造・設備エンジニアリング、生産技術までをインテグレードした都市型オフィスです。現代建築の課題、新しい架構システムの実現に挑戦した私達のデザインは、「建築と技術の融合・触発・統合の有様とそれを志向する理念」を掲げるアーキニアリングデザインそのものだと感じ、AND賞に応募しました。(三橋)
【講評】この計画はオフィスの成熟した既存技術を新たな視点で適材適所に再構成した優れた提案である。「イタリア街」という特異な都市街区の計画で求められる景観に合わせるため、レンガ風の色彩の外壁とアーチというある意味見慣れたボキャブラリーで、一見するとラーメン構造にランダムな外皮を纏わせた「流行の」のビルに見えてしまうが、詳細に読み解くと、「ドミノ・システムのオルタナティブ」と語っている意気込みの理由がわかる。基本的には軟弱地盤と地震国に対応する免震構造をベースにして、地上部分を街並みに調和する大スパンのSRC構造アーチを基壇とし、その上のオフィス部分を「千鳥積層型外壁PC架構の外壁」としている。この外壁は建築・設備・構造をインテグレートさせたデザインコンセプト「現代の組積造」と呼ぶ「正直」な素材と力学による技術の詰まった外装である。地震力を受ける柱と梁のないPCブロックがそのまま内外壁となっているため、外観は日射調整と自然換気口を隠す彫の深い表情となっていると同時にセンターコアに耐震部材のないのない「薄く透けたコア」を生み出している。アーキニアリング・デザインとして相応しい都市型中規模オフィスの優れた提案であると言える。(堀越)
入賞
SKIP JOINT SYSTEM(東京木工場 来客棟)
応募代表者:山田 徹(清水建設)共同応募者:菊田 大典、加藤 ひかる、島田 大偉、貞広 修、谷口 尚範、佐藤 彰、志村 雄、菅原 和正、和田 昌樹(清水建設)、小野塚 真規(オノツカ)

【講評】安価で入手しやすい一般流通木材を用いた架構システム。一本の材を、長手方向に3つに割り、中の材を半分ずらして合わせ、それぞれでアーチを形成する。接合部にはくさび材を挟んでおり、木材の収縮にも、くさびが落ちて締まることで対応するという。細い木を圧縮材として使うアイデアは意表を突くもの。シンプルなデザインでありながらも、低ライズの天井が美しく仕上がっている。今回、実現した東京木工場来客棟は、アーチのスパンが10m程度だったが、アーチを構成する材の枚数を増やし、くさびの角度を工夫すれば、40m以上の大スパンも可能だという。体育館、工場、駅などへも展開が期待できるシステムだ。(磯)
MIYASHITA PARK 立体都市公園をなめらかに包む天蓋架構
応募代表者:山﨑 和宏(竹中工務店)共同応募者:美島 康人、町田 巌、檜垣 政弘、鈴木 康平(竹中工務店)

【講評】渋谷駅近くにある立体都市公園で、様々な制約の中で多くのブロックをつないで空中公園を実現し、都市に新しい人の流れと賑わいを生み出している。今回応募されたのは、長さ330mにわたるその屋上公園を覆う天蓋架構で、連続したアーチ架構の間に張られたワイヤーメッシュにやがて緑が生い茂る。アーチの形状は緑の面積を最大化するように計画されている。また、長大な屋上空間に一体感を与え、活力あるパブリックスペースとなっている。この天蓋に緑が生い茂れば、今までに体験したことのない緑地空間が実現し、都市にやすらぎと動きを与えることになる。(陶器)
KU11 住みながら少しずつ手を加える手がかりとしての架構
応募代表者:小見山 陽介(京都大学/エムロード環境造形研究所)共同応募者:木村 俊明(名古屋市立大学/KKuma)

【講評】都市の市街地にある住宅である。前面は農地で大きく開かれている景観を活かして、全体をトンネル状の空間としている。そのために、間口方向の壁をなくして、代わりに両側の柱を斜めの部材で補強している。この部分的に取り付けられたように見える斜材は、構造と家具の中間のようにデザインされていて、住人の生活を少しだけ規定しながら、むしろこれからの生活の手がかりとなる姿を想像させる。このような斜材は、近代の合理的な思想では評価することが難しく、邪魔な存在としてこれまで排除されてきた。しかし、この小さな斜材は、補強するというものづくりの可能性を、もう一度考えることにつながっている。(福島)