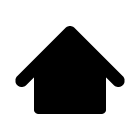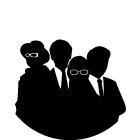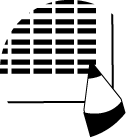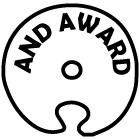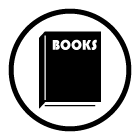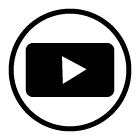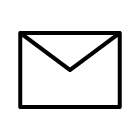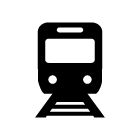第5回 アーキニアリング・デザイン・アワード 2024
選考委員
福島加津也(委員長)(東京都市大学教授/建築家)、陶器浩一(滋賀県立大学教授/構造家)、磯 達雄(建築ジャーナリスト)、堀越英嗣(芝浦工業大学名誉教授/建築家)選考評(総評) 選考評(個別) 冊子PDF
選考評(総評)
第5回AND賞をめぐって
斎藤公男(AND賞実行委員長)
第5回となるAND賞2024の最終選考会は2025年2月8日、昨年と同じ日本大学理工学部CSTホールで開催され、無事終了することができました。心より安堵すると共に、応募された皆さん、選考委員ならびに運営を支えて頂いた運営委員、実行委員の方々に感謝する次第です。
日頃多忙を極める中でAND賞に応募されたプロジェクトからは時代を切り拓く様々な魅力的なテーマが感じられました。そして長時間の熱心な選考を重ねて頂いた福島加津也委員長をはじめ、堀越英嗣、陶器浩一、磯達雄の諸氏に敬意と謝意を表します。
AND賞は現地審査はないものの、優秀賞、さらに最優秀賞を決定する最後の場面まで公開することを大きな特徴としています。建築学会賞やJSCA賞など他の表彰にはあまりみられない難しい選考方法とも言えます。今回の選考会でも各々の選考委員が抱くAND賞に対する評価軸が吐露されましたが、各自の個性をにじませながらも大局的にはぶれない価値観が共有されていると思いました。各委員と応募者との緊迫したやりとりや、委員同士の強いコメントの数々は実に興味深く、まさに「AND賞に学ぶ」の言葉が実感されました。
AND賞への応募数は第1回より第4回まで各々、55件、40件、27件、32件。そして今回の第5回では25件でした。8作品を選ぶことにした一次選考(2024年12月21日)から議論は沸騰し、惜しくも入賞を逃したいくつかはとても気になります。別の機会に是非共もっと踏み込んだプレゼンを聞きたいものです。最終選考に進んだ8作品はいずれも独自のテーマをもっており、個性的な建築的魅力、デザインの美しさと共に強い技術的創意や協働性、普遍的な創造性が読みとれました。
全体的に木造の応募作品が多かったように思いますが、個人的に特に印象的だったのは「YAP Constructo 07 -ノマディック ドーム」が優秀賞を受賞したことです。“テンセグリティ”は私にとって卒業研究のテーマとして以来60年余りの付き合い。B.フラーもその建築・構造化に辿りつけなかったようにその面白さと難しさは色あせません。恒久建築としては我が国では唯一「天城ドーム(1991)」があるのみです。軽量性と仮設性は普遍的テーマ。本来は万博などの場面で挑戦すべき重要なテーマなのですが、なかなか目を見張るプロジェクトは少ないようです。因みに愛・地球博(2003)で実現した「虹のシザーズ」はそれから50回を超える人力による組み立てを行っています。求められるのは美しさと強さに加え、建方・解体・運搬・収納が容易となるシステムとディテール。「適合建築」の新しい可能性を拓くプロジェクトとして、今後の展開を期待したいと思います。
21世紀もすでに1/4を過ぎようとしている今日、20世紀の建築に比べ、最も影響を与えているもののひとつはいうまでもなくコンピューターの進化と発展です。もはや情報化時代ではなく「情報化社会」であり、デジタル技術やアルゴリズムの浸透のスピードと多様性はとどまる処を知らない感があります。時には方向性を誤ったり、過剰なエネルギーの浪費を促すこともありそうです。一方、BIMやAIはあくまで人間の思考や技術的判断や効率化のための手段(ツール)のひとつ。それ以上の存在ではない、との声も聞こえてきます。
そうした状況を踏まえて、此度、建築学会における2025年度開始の特別研究委員会として「アーキニアリング・デザイン研究会」を立ち上げることにしました。テーマは「情報化社会におけるアーキニアリング・デザインのゆくえ」。今後のAND賞の応募や選考に関わる論点のひとつとして議論を進めたいと考えています。委員会で企画するフォーラムなどにはさまざまな分野の方々に登壇して頂き、関心を抱く多くの方々の自由な参加を期待しています。
思考と工夫、時には閃きを求める構想力、ものづくりへのリスペクトとそのプロセス(設計~施工)を進める情熱。ヒト・コト・モノの物語をつなぐこと。不安を抱きながらも夢や希望をもちながら、そうした思いを問い続けることこそが「AND賞」が目指すものではないでしょうか。
選考経過と総評
福島加津也(AND賞選考委員長)
工学と美学の融合を目指すアーキニアリングという思いは、現代社会の多様化の中で、環境や建設、改修やものづくりにまで拡がります。このため、AND賞の選考委員も多様になるでしょう。経験豊富な建築家として堀越委員に、構造設計にとどまらない幅広い活動をしている構造家の陶器委員、日本では貴重な建築批評家として磯委員に、若輩の建築家として福島、という4名で構成されています。
今回の一次選考では、日本有数の大手建設会社から、若手の建築家やアーティストまで、幅広い分野から25作品の応募を得ました。昨年度は32作品でしたので、今年度は少し減じたことになります。その中から、AND賞の意義にふさわしい8作品が入賞として選ばれて、最終選考に進みました。
当日のプレゼンテーションは発表が4分、質疑応答が6分の計10分です。登壇者のみなさんの説明は、近年にもまして木造への関心が高まっていたことが印象に残ります。
そうして、最優秀賞を決める選考が始まりました。例年通り、ここで4人の選考委員がそれぞれの選考基準を明らかにしました。今回のテーマは、堀越委員が「既視感の延長線上」、磯委員が「社会への影響力」、陶器委員が「アーキテクトとエンジニアの対話」、福島が「つくることのデザイン」です。その後、1人4票で投票を行いましたが、満票の作品が「VOXEL APARTMENT」、3票が「十津川村災害対策品部拠点施設」、2票が「富士ソフト汐留ビル」、「人工林の課題からつくられた小径間伐材の建築」、「YAP Constructo 07-ノマディック ドーム」と2票以上を獲得した作品が5つになりました。例年と等しくここから4作品に絞るため、1人2票でもう一度投票を行ったのですが、最初に2票を獲得した3作品が僅差となり、選考委員による議論でも優劣がつきません。さっそく、AND賞特有の緊張関係が始まりました(笑)。選考委員と実行委員会の協議の結果、例年とは異なりますが当初の5作品を最優秀賞の選考に進めることとなりました。しかし、昨年度は例外的に最優秀が2作品となってしまったため、今年度は必ず1作品にするように、と斎藤公男実行営員長から選考委員長に厳命が下っています(笑)。次の審査がさらに心配です。
残った5作品には、1分で追加アピールをしていただきました。その内容を加えて、今回はより詳細な得点差がつくように、各審査委員が3点と2点と1点を投票するようにしたのですが、なんと「十津川村災害対策品部拠点施設」が7点、「VOXEL APARTMENT」も7点、「YAP Constructo 07-ノマディック ドーム」が6点と、3作品が僅差という結果になってしまいました。ここまで僅差になるとは、もうこれは選考委員長に対する何かの試練なのでしょうか。それぞれの作品の特徴も、地元産材を用いた地方の木造建築、壁式フィーレンデールの都市型集合住宅、セルフビルドのパビリオンと全く異なります。
しかし、さらに目を凝らして投票内容を見てみると、3点を入れている選考委員が2人いるのは「十津川村災害対策品部拠点施設」だけであり、他の2作品は3点を入れている選考委員が1名であったため、このわずかな差を持って、今年度の最優秀作品を「十津川村災害対策品部拠点施設」とすることになりました。優秀賞は「VOXEL APARTMENT」、「富士ソフト汐留ビル」、「人工林の課題からつくられた小径間伐材の建築」、「YAP Constructo 07-ノマディック ドーム」の4作品です。
今回も大変難しい最終選考となりました。毎回ここまで票数が均衡するということは、AND賞の評価軸が多様だからでしょう。その特性からすると、最優秀を決めるということには適していないのかもしれません。しかし、幅広く奥深いアーキニアリングの世界を、目を閉じて手探りで進むようなこの選考会が、混沌としたように見える現代の建築界を励ます一助になったとしたら、私たちも嬉しいです。次回の審査に向けて、さらなる応募をお待ちしています。
選考を終えて
磯 達雄(AND賞選考委員)
これまでの回よりも応募数は減ったが、作品のレベルは総じて高い。一次の書類選考でも、どの作品を残すのかが、最後の最後まで決まらなかった。当初は選考委員の中でも支持が少なかった作品が、議論の中で評価が高まり、最終的に通過したケースもあった。最終選考に残った8作品は、小住宅から都市公園まで、スケールも用途も様々で比較するのが難しい。いずれが最優秀作になるか、予想が付かない。対面のプレゼンテーションが結果を大きく作用するかもしれないと思いながら、それを聴いた。
それを踏まえて、最終選考会で最初の中間投票で票を入れたのは、「SKIP JOINT SYSTEM」「十津川村災害対策本部拠点施設」「VOXEL APARTMENT」「富士ソフト汐留ビル」の4作品である。
「SKIP JOINT SYSTEM」は一般流通木材による架構のデザイン。木造による大スパンを、従来の主流だった大断面集成材ではなく、規格材や小径材で実現しようとする取り組みは、これまでのAND賞応募作にも見られたもので、昨今の社会的要請と言える。この事例では、木材を長手方向で3つに挽いて、それをずらしながらつないでアーチにしている。低いライズのヴォールト天井がシンプルに美しくでき上がっている点からも、これを推した。
「十津川村災害対策本部拠点施設」も木造で、地産の製材を用いたもの。こちらは柱の間を斜材が村章の「菱十字」をかたどるようにつながり、耐震性を確保する。この斜材が周囲の民家と共通する屋根の形に波及し、ファサードのデザインにも現れる。構造・意匠と地域性が強く結びついたデザインだ。
「VOXEL APARTMENT」は1辺が2750mmの立方体がタテヨコに自在につながり全体を構成している。袖壁、垂れ壁、腰壁がフィーレンディールトラスとして働き、キャンチレバーの構造を成立させているという。同じ意匠設計者による「十津川村」と似て、ひとつの構造システムが建物全体に散らばっている。
「富士ソフト汐留ビル」はPCブロックによる組積造の外郭架構。前回のAND賞ではコンクリート打ち放しというレガシーに新たな可能性を開いた作品を最後まで強く推したが、今年の候補作でそれに類するのが、この作品かもしれない。開口の小ささについても、それがメリットと位置付けられていて隙がない。
この段階で票を入れなかった作品についても触れておく。「人工林の課題からつくられた小径間伐材の建築」は「SKIP JOINT SYSTEM」と似たテーマを扱い、複雑そうに見えて実は単純な架構のシステムをこちらも実現してる。しかし「この場所で採れる間伐材」をうたいながら、製材にはそれなり離れたところまで運ぶ必要が生じていて、その点が気になり、推すのをためらった。「YAP Construction 07」は、繊細な構造が美しいものの、「旅するテンセグリティドーム」とのコンセプトに対応する、輸送のデザインに説得力がなかった。「MIYASHITA PARK」は立体都市公園の意義は認めるものの、天蓋架構のデザインと緑化システムの結び付きに弱さを感じた。「KU11」は小住宅に偏心ブレースを適用したもの。適度なさりげなさに惹かれたが、今回は構造がより明快な他の候補作に軍配を上げた。
「十津川村~」「VOXEL~」「人工林~」「YAP~」「富士ソフト~」の5作に絞られてからの2回目投票では、「十津川村~」に3点、「富士ソフト~」に2点、「YAP~」に1点を入れた。他の選考委員の投票結果と併せて、最優秀賞には「十津川村~」が選ばれた。
「十津川村~」は、地域に由来する建物形態や材料調達から、構造のデザインへと展開し、それが建物全体を規定している。建築と技術の融合を果たしたものであり、結果として、AND賞の理念に最もふさわしい作品を選び出すことができたと考えている。
陶器 浩一(AND賞選考委員)
AND賞も5回目の選考となりました。今年もビッグプロジェクトからフォリーのような小作品まで多種多様な応募作が並び、例年同様選考に頭を悩ませると共に、応募作が多様であること故にAND賞の目的が浸透してきたようにも思います。多面的にある評価軸の中から何に重きを置くのかは選考員により、年により変わり、これもAND賞らしいともいえます。私は今回「対話」に重きを置きました。アーキテクトとエンジニア、設計者と施工者、建築と社会、それぞれの対話の中で建築が高められてゆくことこそがANDの精神といえるので、そのプロセスを重視したいと思いました。その根底にあるのは「正直」であることだと思います。技術を誇張するものでもなく、デザインを押し付けることでもなく、さりげない“技術”とデザインとの対話が新たな空間を生み出し、まちに働きかけているような作品に注目しました。
最終選考で発表された8作品はいずれも様々な視点で“AND”の理念を追求したものでしたが、私が一次で投票したものは「十津川災害対策本部拠点施設」、「VOXEL APARTMENT」、「人工林の課題からつくられた小径間伐材の建築」、「MIYASHITA PARK―立体都市公園をなめらかに包む天蓋架構―」の4作品で、投票には至らなかったものの「ノマディック ドーム」も気になった作品です。 「人工林の課題からつくられた小径間伐材の建築」は小径間伐材を用いた屋根架構が印象的で、不完全なトラス架構を並べて直交方向にはしご状の梁を挿入することにより、複雑な接合部をつくることなく軽快な空間をうみだしています。「ノマディック ドーム」は南米チリで学生ワークショップにより作られたテンセグリティドームで、そののち日本で再構築されています。素人の手で構築された空間としては大きなもので、なによりも美しい。自らの手で立ち上げたこの空間を目の当たりにした時のワークショップ参加者の感動が目に浮かびます。美しいものは人に感動を与え、これもANDの大切な要素だと思います。 「MIYASHITA PARK」は渋谷駅近くにある立体都市公園で、様々な制約の中で多くのブロックをつないで空中公園を実現し、都市に新しい人の流れと賑わいを生み出しています。この天蓋に緑が生い茂れば、今までに体験したことのない緑地空間が実現し、都市にやすらぎと動きを与えるでしょう。
今回最も印象的であったのは、「十津川災害対策本部拠点施設」と「VOXEL APARTMENT」でした。いずれも藤村龍至さんの作品ですが、「対話」という視点でいえば、前者はエンジニアとアーキテクトの対話、後者は建築と都市との対話が特徴的だと思います。 「VOXEL APARTMENT」は2750㎜グリッドを基本とし、その架構の反復で凸凹のある空間を作り出しています。居住空間、特に外部空間に多くの居場所と変化を与えていますが、それよりも周辺環境に動きを与えている効果が大きく、画一的な都市の表情に動きを与える、まちに開いた建築だと感じました。
「十津川災害対策本部拠点施設」は中山間地域の災害拠点施設ですが、地域で取れる材木の種類を丹念に調べ、欠点も有するそれらの材を活かしながら特徴ある空間を構築してゆく設計プロセスと、その過程での設計者の、素材、地域、技術に対する誠実な姿勢にとても共感を覚えました。ひし形で架構を構成するというひとつのシステムでありながら、部材配置をパラメトリックに変化させることにより動きのある特徴的な空間を素直に実現しています。ダイナミックな架構をつくろうというエンジニアの欲でもなく、恣意的なカタチをつくろうというデザイナーの欲でもなく、素材に素直に向き合ったプロセスが特徴的な空間をうみだし、それが地域や社会に刺激を与えているという点で、この作品に最終票を投じました。
堀越 英嗣(AND賞選考委員)
現在さまざまな建築の賞が毎年選ばれています。これまで私自身も一建築家として、自らの仕事の意義について素直に様々な建築家、評論家、技術者等の評価を聞くことで次への仕事の糧にしてきました。時に落胆し、勇気付けられてきました。その時に心に響く言葉や講評は、選考委員の方々の正直で偏見のない素直な論評でした。経験を積む中で、今度は選考者の立場となることが次第に増え、先に述べたように、正直に、偏りなく、真摯に応募者が目指している方向を読み取り、多くの人が良い影響を受けるであろう仕事について意見を述べるべきだと感じてきました。そのため、時には選考委員の中での意見の相違や、対立も生まれることがありますが、自らの能力の限界の中で、真摯に、正直に評価する姿勢は貫くべきだと信じています。年齢とともに思考の柔軟さがなくなると言われていますが、逆に多くの経験が視野を広げてきていることを実感しています。特に大学での研究・教育と設計の実践を並行してきた視点から、学生たちの新鮮な見方や、社会の硬直的な体制等との狭間で思考を常に新鮮な状態に保つことを心がけてから、少し気持ちが楽になり、客観的に批評、評価ができるようになったと思います。恩師の一人でもある、山本学治は構造研究者、歴史家、評論家という多様で総合的な目線で、建築の意義や価値を述べています。そのことが、斎藤公男先生のアーキニアリング・デザインの視点に通じ、継承され続けていることに可能性を感じ、今回5回目となるAND賞の選考委員を一層新たな気持ちで継続させて頂きました。5回の賞の選考を通して、他の建築の賞との違いが次第に見えてきたところです。一番は応募者の立場です。建築家はもとより、構造家、技術者が多様なスケールとジャンルで応募しています。それを、多様な立場の選考委員が評価することで、単なる流行のデザインや、完成度での評価とは異なる、哲学と技術の統合に価値を感じる方々の応募を評価することが意義深いと思います。今回は25作品の応募となり、前回と比べ数は多くはなかったが、提出された作品はそれぞれの分野で特別な意義とこだわりの作品が多かったと思います。逆に際立った大作、問題作と言えるものが無いように感じたことが、プロフェッショナルで多彩な視点の応募というAND賞が目指す本来の意図に合っているのではないかと思います。
一次選考の最初の投票は多彩な提出案と多彩な選考委員の組み合わせから、票は少し分散しましたが、集計すると複数の票が集まる作品は限られていました。最終選考に進んだ作品の中で、最優秀賞となった「十津川村災害対策本部拠点施設」は、山間部の施設として環境フットプリントを抑えた地場産材を全数検査でかつ適材適所に100%採用していること、材料の強度を保ため鋼板を製材に切り込むのではなく挟むなど、きめ細かく少しずつ調整する仕事の進め方は、大量生産で規格材を揃えることで、生じてしまう端材を減らすなど、本質的でサスティナブルな仕事の進め方と言えます。そのような一貫した姿勢は抽象的幾何学的明快さを優先するのではなく、適切な空間サイズに合わせた「歪んだ」菱形トラスの構造が、むしろ正直さを表していることに気付かされる。立ち止まりながら進める手法は、これからの建築デザインのあるべき可能性を示している。最後まで残った「ノマディック ドーム」は機能性、実用性を超える美しい垂直性が崇高さを感じる場を作るテンセグリティドームであり、フィーレンデールトラスで離散的構造を忍ばせて都市の立体的外部空間を生み出している「VOXEL APARTMENT」と共に優秀賞に相応しいと思います。