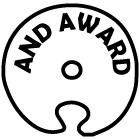斎藤公男
19世紀末、明治初期の日本には「建築」の言葉もなく、「近代化」とは「西洋化」のこと。そこには2つの目標があった。ひとつは石造や煉瓦造という新しい技術の習得であり、いまひとつは西欧的な美的感覚の吸収である。この頃の建築家は新しい耐火的な組積造をマスターする一方で、意匠を中心とする設計意識を高めることに熱意を示していた。
1886年(明治19年)、日本建築学会(造家学会)が創設され、辰野金吾が会長(代表)となった。この時期、欧米ではすでに鉄骨造が普及し、RC造の芽生えと共に近代にふさわしい構造システムが確立されつつあった。この変化に気づかず石造や煉瓦造が今後の日本建築の基本だと信じ続けた日本の建築家たち。この流れは明治末期まで続く。当時、辰野金吾も述懐していたという。「日本には地震があって欧米風のArchitectureでは安全性に自信がない。困ったものだ。」(「佐野利器と日本大学高等工学校」日本大学桜門建築会創立80周年記念誌、2002.10)
大正期に入ると、耐震性を考慮した日本独自の構造技術を模索する動きが加速する。すぐれた研究者たちは「構造家」として、日本の、今日に続く近代建築を拓いていった。そうした先駆者を牽引したのは言うまでもなく佐野利器(1880-1956)である。
濃尾地震(明治24年)の惨事は当時小学校4年生であった佐野の脳裏にどう刻まれたのであろうか。仙台の高校時代から建築学会に学生会員として入会していた佐野は大学入学当初から欧米のSchool of Architecture(建築学部)風の建築教育になじめず悩んでいたことはよく知られている。大学卒業の3年後(明治39年)にはカリフォルニア大地震の調査団に加わり、さらにその5年後には3年間の欧米への留学。留学先のドイツから投稿した佐野の一文がある。「建築家を大別したならば、美術を主とする建築家(芸術家)と科学を主にする建築家(技術家)の2つとなすことができる。(中略)日本の建築家は主として須く科学を基本とする技術家であることは明瞭である。」(建築学会雑誌275号、明治44年)
1987年5月、小さな冊子がつくられた。題して「小野薫先生を偲ぶ」。発行者は偲ぶ会の代表、田中尚・加藤渉。没後30周年の記念誌という。寄稿者は13人。武藤清、坪井善勝、高山英華、前田敏夫、伊藤喜三郎、小堀鐸二といった著名な方々の名が連なる。30年の歳月を越えて寄せられた小文に溢れる回想の数々に心打たれる。小野薫(1903-1957)は当時学部長であった佐野利器に請われて昭和4年から日本大学教授であったが、昭和14年の佐野退陣と共に退職。昭和16年には内田祥文に請われて満州から東大第二工学部設立のため帰国している。終戦と共に日大理工学部の再建にも尽力した。私が日大に入学したその年に亡くなられたので直接お会いしていないのが残念であるが、恩師の斎藤謙次、小野新(薫先生のご長男)の両先生を通じ、並々ならぬ大きな人格・人柄・才覚を感じている。構造力学の大家、絵画の達人、熱心な教育者、スポーツとお酒が好き、知より情、などなど―。今日、自分がここにいるのも薫先生のおかげだと思わずにいられない。冊子の中で坪井善勝(1907-1990)が書いている。「東大第二工学部(現・生産技術研究所)の設立者、日大理工学部の基礎固めの功労者、骨組力学の創始者、…建築学の教育者としての小野薫先生の天才的活躍の短い生涯(53歳)は日本の盛衰と一体となった波乱の歴史である。(中略)小野先生をはさんだ20世紀は19世紀から今まで、明治維新、第二次大戦、日本の一時崩壊と復興と目まぐるしく早かった日本の歴史を感じて止まない。もう少し長生きして頂いて今日の混乱期に何か明るいご教示を念願するのは私だけではないはずである。初めて会ったスペインの偉才、故エドワルド・トロハ(1899-1961)にまず親近感を覚えたのは、何となく小野先生を重ねたからであった。1959年秋のことである。」
小野薫による「撓角法」(1948)は骨組架構のバイブルといわれるが、同じ頃、小野は当時日本最大の曲面構造―「鶴見倉庫のRCシャーレ」(1951)の構造設計を行い、加藤渉の協力を得て実現している。戦時中、ガソリンタンクを爆片から守るための直径40m、高さ9m、厚さ約40cmの円筒RC外壁のリングの上に薄肉シェル(中央厚さ10cm)をのせたもの。採光用のガラスブロックが円環状に美しく配されている。倉庫としての再利用も興味深い。因みに加藤は佐野利器工学部長の辞任騒動の学生リーダーであり、斎藤謙次と共に佐野の復帰運動に力を注いでいる。
1951年といえばまず想起されるのは「リーダーズダイジェスト東京支社」の出現。建築家A.レイモンドと建築家P.ワイドリンガーの協働である。あたかも1本足で爪先立つバレリーナのようなデザインと特異な構造形式が大きな議論を呼んだ。いわゆる「リーダイ論争」である。日本が戦後の混乱期を抜け出したこの時代、この時の中心的論者は東大の同期で建築研究所にいた竹山謙三郎と坪井善勝(当時44歳)であった。かつて武藤清(1903-1989)に学んだ坪井は小野薫の招きで第二工学部に籍を置きながら、戦前からの「平板構造」に続き「壁式構造」に取り組んでいた。地震国日本の耐震技術の安全性を自負していた新任教授・坪井は声を大にしたに違いない。この論争の高まりは驚きであり、建築会、特に建築家へのインパクトは大きかったが、日米の考え方もあり、議論自体はあいまいに終わった。10年後の解体時の水平加力実験によって当時予想された以上に建物の剛性は高く、固有周期もほぼ妥当であった。処女作というべきか。P.ワイドリンガーには構造設計者としての確固たる自信がここから生まれたにちがいない。「リーダイ論争」の当否は別として、より重要なことは、ここにわが国の「構造デザインの夜明け」ともいえる新しい舞台がつくられた、ということであろう。 坪井の中に芽生えた視点は2つと考える。ひとつは当時の多くの建築家が予感し、期待したであろう構造家像。すなわち基準法や既成の型にはまらない新しい建築空間の創出には意欲的な構造設計者のサポートが必要であること。両者の有機的協働が強くイメージされたにちがいない。研究者や技術者とは異質な職能としての「構造設計者」や「構造家」への道が意識されてくる。いまひとつはリーダイ論争の陰で認識できなかった柱頭の精緻なピンジョイントに象徴されるようなディテールや力学的メカニズム。そうした創意につながる構造デザインへの興味であろう。
それからわずか2年後のことである。1953年、運命に導かれたとも言われる「愛媛県民館」の完成と共に、坪井善勝・丹下健三の協働が本格的に始動しはじめる。それに続く有能なエンジニア達によってわが国の「構造デザイン」への道が展開されていったのだ。
今思えば奇跡のような物語である。「愛媛」の前には「広島」がある。丹下は終戦直後から設計の中にシェルを度々とり入れている。1949年「広島平和記念公園」のコンペを勝った丹下は、1951年「広島子供の家」の設計を依頼されるが、魅力的な朝顔シェルの初期スケッチは沖種郎によるとされる。丹下の指示により沖は構造家・小野薫を訪ねた。あいにく不在だった小野に代わって相談にのったのは坪井善勝。丹下・坪井の協働がスタートした奇跡的瞬間といえようか。こうした出会いの物語は他にもありそうである。たとえば、戦後初めて登場する専業構造事務所を開いた創設者には、横山不学(1903-1989)と木村俊彦(1926-2009)がいる。横山は教室主任の佐野利器の指示で日本銀行建築部へ勤務し、その後さまざまな官公庁の役人として約20年間、技術的実績を重ねた。「役所勤めはやめて、一緒に新しい建築をめざそう」。そう声をかけたのは建築家・前川國男(1905-1986)。そして横山が設計事務所を立ち上げる一年前には木村が前川事務所に入社している。数学と絵画の才もあった木村を建築の世界に誘い、さらに卒業後、前川事務所を紹介したのは指導教授の小野薫であった。そして「しばらくは構造をやってくれないか」。そう口説き落としたのは、ここでも前川であった。「自分は小野先生に騙され、前川先生に煽てられ仕立てられて構造設計者になった」と、木村はよく冗談交じりに話していた。佐野利器、小野薫、前川國男―そうした先達が居なかったら構造デザインの世界は拓かれなかったかもしれない。構造設計に進む軌跡や動機が多様であることは、若い人達にとっても自身の“選択”を考える上で参考になろう。
ところで坪井が「構造デザイナー」としての役割と魅力にめざめ、それを指向すべきだと確信させたものは「晴海ドーム」(1959)だったと述懐している(「直観の復活」建築雑誌、1986.5号)。いろいろなプロジェクトを通じて次第に、あるいは突然、構造デザインへの関心が深まっていく。これも構造設計のおもしろさといえよう。