

神田順
20年ほど前から、わが国の林業の課題が、農水省や国交省でも大きく取り上げられ、建築における国産材の活用が、さまざまな形で現れてきている。木材自給率も18%くらいから40%くらいまでに回復しているようである。特に公共建築では、10年ほど前に、木材利用の推進を法律にまで制定し、国の政策としても展開している。
このたび、岩手県の住田町の町役場を訪れて、木造建築のことを思った。人口4600人ほどで、山間地にあり、「日本一の林業のまち」を目指している。そのためのシンボル的な町役場は、斜めの格子壁と木造の張弦梁による現代工学を体現した木造建築である。
話題になった新国立競技場においても日本全国の木材が多用されている。木材利用推進という意味では、プラスチックやアルミを使うよりも優れた選択であると思うのだが、改めて置いて行かれたのが、大工棟梁による伝統木造の住宅建築である。
戦前までは、建築基準法もなく、木造住宅は仕口・継手は大工の手刻みによる伝統工法によっていた。それが、大工の腕に依存しないでも金物でつなげばよいことが、建築基準法上の木造在来工法として位置づけられてしまった。大量生産・工業化の波は建築界にもやってきて、ハウスメーカは、鉄骨系、RC系も含めて、多くのシェアを占めるようになり、わが国の住宅から伝統木造が押し出されてしまった。効率化が質の良さを駆逐した例である。
神社・仏閣にあっては、一時はほとんどがRCに傾いたときもあるが、今は、また古来の木造が復活しているように感じている。歴史・文化ということを考えれば、伝統木造がこのような形で消えることはないと思う。しかし、量的には、住宅とは比べ物にならない。
住田町役場には、樹齢100年を超える杉の柱が4本使われていたり、引っ張り材としての木材に伝統的継手が用いられたりするが、象徴的に扱われているにすぎない。実際にまちの中で、伝統木造の家がどれだけ作りやすい環境になっているかは大いに疑問である。
その土地に育った杉や檜を、大工が自分の目で見て、柱や壁に選択し、製材した上で加工する。そんな木造住宅であれば、補修や改築も、地元の大工の手で対応もしやすい。建築としては、理想的な持続可能社会ではないか。社会制度的にもそこまで踏み込んで、自治体としての対応を期待したいものである。
今年の1月に増田一眞氏(享年89歳)が亡くなった。多くの大工や構造設計者に向けて、木構造の教材を自ら作り、多くの地域で講義を行ってきた。この9月には追悼の会が計画されている。氏は、構造設計は工法を考えなくてはいけないことを強調し、また、RC造については、プレキャストの活用を発信していた。伝統木造については、1930年代まで広くその技術は発展し、多くの大工が育っていたのに、今や急激にその数を減らしている。
集成材が使いやすいことやプレカットが効率的であることのすべてを否定することはないが、地場の木材を人の目で選択し手で加工するという原点を失うことなく、循環的に森と住まいが回っていく社会を育てたいものである。「構造は美しくなければいけない」は、増田一眞の言葉でもある。伝統木造を思うとき、アーキニアリングの実践者としての増田の存在が大きかった。未来に向けて、これからも生かすべきわが国の技である。
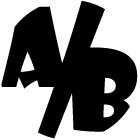

開催日時:2023年09月09日(土)14:00~
トーク:斎藤公男

関東大震災から100年目を迎える契機に、防災科学の視点から関東大震災を振り返り、過去から現在を精査しつつ、未来への展望について議論する。特に2023年7月8日の学術フォーラム「関東大震災100 年と防災減災科学」での知見を整理しつつ、地震・地震動、都市計画、災害医療、情報・社会の4 つの観点で、学協会の枠を超えた情報共有を行う。
ご案内PDF、ぼうさいこくたい2023特設ページ